![]() �V���[�Y�@��y�Ɋw�ԁ@�@
�V���[�Y�@��y�Ɋw�ԁ@�@
�����P�X�N�P�P���U���@��{���̈��
���z���@�@����Ƃ��q�����@�u����
�@�P�P���U���A�{�Z�̑��Ɛ��Ō��z�ƂƂ��Ċ���Ă������Ƃ��q����̍u������J�Â������܂����B�ی�҂̊F�l������������Q������������Q���ԁA220���̃X���C�h�𓊉e���Ȃ���e���r�ԑg�u���I�r�t�H�[�A�t�^�[�v���̂܂܂ɍŐ�[�̌��z�̂��b�����������܂����B���b�̈ꕔ���Љ�܂��B���N�x�̃L����������̈�Ƃ��Ă��̊����������邱�Ƃ��ł��܂����B�g�߂Ȑ�y����E�Ɛl�Ƃ��Ă̂��̂̌����l�����ڂ��������邱�ƂŐ��k�͐i�H�ɂ��Ă��邢�͐������ɂ��Đ[���l����@��ɂȂ�܂����B���k�ƂƂ��Ɋ��ӂ������Ǝv���܂��B
 �����b������
�����b������
�@����ɂ��͎�{���w�Z�̊F����B���w���ɘb������̂͏��߂Ăł��B ���\�N�O������{���w�Z�̐��k�ł����B�����̂��b�͌��z�ƂƂ����E�Ɓi�E�\�j��I���R�₫�������B�d���̓��e���啪��B����̐l���ɂ��āB���w����̎v���o�Ȃǂł��B
�@�q�ǂ�����ƕ��Ƃ̎v����
�@���͎O�l���傤�����̎O�ԖڂŎ����S�̉����Ȏq���ł����B���܂肩�܂��Ă��炦�Ȃ������Ƃ����L���������̂ł����A���͎��̂��Ƃ������ƌ�����Ă���Ă����傫�ȑ��݂ł������Ƃ������ƂɍŋߋC�Â��܂����B�D��S�����ȃK�b�c��������肦�ȏ��̎q���ꐶ������ĂĂ���܂����B���Ƃ͈ӌ������������قǂ̒��ł͂Ȃ������̂ł������ƂȂ��Ԃ����Ă��܂��B�����20��ł����B�ŏ��ɊF����ɕ��̎O�̌��t�����b���܂��B�@�@���̂ЂƂ́u����قǓ��𐂂炷��䂩�ȁv�傫���Ȃ��Đ������Ă����đ傫���Ȃ�قǍ��݂��瑊��������낷�̂ł͂Ȃ��Ď����̕�����l�l�Ɍ��g����悤�Ȏv���ł��邱�ƁA���S���Ȃ����ƁB��ڂ́u�w��ɂ͒j�������Ȃ��v���ƁB���̌��t�������n�łȂ����Ȍn��I�����Ǝv���Ă��܂��B�O�߂́u���̒����܉~�ʂ̌����猩�Ă����Ȃ��v�Ƃ������t�ł��B�U��Ԃ��Ă݂�Ɛe�̌��t�͂��肪�������̂��ƋC�Â��܂����B
�@���z�Ƃւ̓�
�@���w�Z�̂Ƃ��͒m�肽���艮�A�D��S�����ł����B�����邱�Ƃ��D���ƌ������͉����H�v���邱�Ƃ��D���ł����B��{���w�Z�A�O�����Z�A���嗝�H�w���@��w�@�ɂ������܂����B���̌�傫�Ȍ��z�������ɂ����܂����B�����͑g�D�łȂ��Ƃ���Ŏ����������悤�ɂȂ��Ă��������Ƃ������܂����B���̑O�ɐ��N�ԋ߂��������ɉ��Ԃ������Ă���Ǝv���܂����B�����ł�����ĂP�����z�m�̎��i���Ƃ��Ă���Ɉ�N�Ζ����܂����B���̌�C�O�ɔ�яo���Ă������ƂɂȂ�܂����B�����̓N���G�C�e�B�u�Ȏd���A���{�̖��ɗ��d�������߂ĊC�O�ɔ�яo���Ă���������ł����B���͒��w���ł������̗͂����߂���D��S�������肷�邽�߂ɊC�O�Ɏ��R�ɂ������Ƃ��ł��܂����A�����̃Z���N�g�V���b�v���f�U�C�������薭�������̃z�e���Ȃǃ`�����X�Ɍb�܂��r�I�Ⴂ�����ɐv�ɓ�����d�����ł����̂͂��̂P�O�N���������Ǝv���܂��B
�@�f�U�C���̎d��
�@���̎ʐ^�͂Ȃ�ł��傤�B����͐�������ł��B�Q�N�O�ɔ��\�������̂ł��B���z�ƂƂ����ƌ�����Z��A�C���e�����l���܂������̂悤�Ȑv�̈˗�������܂��B���̃f�U�C���̂��b���������������ɂǂ�ȃf�U�C���ɂ��悤���ƈꐶ�����ɍl���܂����B�����Ɛl�̕�炵�̈��S���S�͈�ԑ傫�ȃe�[�}�ł��B��̌`���l����ɂ������Ă��[���l���܂��B�����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���낢��l�����������ɐ��̌������`�ɂ������Ƃ����v��������܂����B���܂ꂽ�̂����̂�琅���ł��B�F����Ɠ����悤�ɐፑ�ň�������Ƃ��珬������������~���Ă������� ���S�̂ǂ����ɏĂ��t���Ă����̂ł��B�W�����ꂽ�Ƃ���������̕��X���犴�z�����炢�܂����B�u��i�ɐ��̔g�䂪�ʂ��Ă��܂����ˁB�v���X�B���������̂��f�U�C�����������Ȃ̂ɂ��낢��Ȋ��z�����������܂����B
�@�E�l�����Ɉ�Ă���
�@���z�͊����܂łɂT�������炢������܂��B�����ȋƎ�̕��X���W�܂��č��グ�Ă����̂����z�ł��B���̓^���X���̎q���Ƃ��Ĉ炿�܂����B���͕��Ƃ̎q�������̂ł����ċx�݂̏h��͂T�O�l���炢�̐E�l�������Ă����H��ł���Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�݂�Ȃɂ��炩���Ȃ������Ă����̂����ł��B�����̉�������C�T�I�ȁA�F�B�Ƃ�ނ̂������Ȋw��������߂����Ă����̂������̃X�^���X�ł����B���z�ƂƂ��Ď����������܂��������g�D�ɏ�������̂����ł����B�ł��A��̉Ƒ��������d���͋��͂��邱�Ƃ���Ȃ��Ƃł��B�E�l����̒��Ŏ��͎��R�̂ɂȂ�܂��B����͎������E�l�����Ɉ�ĂĂ�����Ă������Ƃ��炭����̂ł���A�����̃o�b�N�O���E���h�Ƃ�������̂ł��B���̂��Ƃɂ��ŋߋC�Â������Ƃł��B
�@�����ɖڂ�������
�@�V�����ł����R�ɂ��Ă��邢�͊��ɂ��čl���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B���R������ɑ��ĊS�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����@�^�����̏\�N�E��\�N�}���ɍ��܂��Ă��Ă��܂��B���͏����ł��̂ł��̂��Ƃɂ��Ă͂ƂĂ��q���ł����B�j���̌��z�Ƃ������������ƂɊ�@�ӎ������悤�ɂȂ��Đ��̒����}���ɕς��܂����B�F��������ꂩ��₢�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��e�[�}�͔��ɏd�����̂��Ƃ������Ƃ���������Ă���������Ǝv���܂��B
�@2050�N���猻�݂�����
�@�Q�O�T�O�N���獡�����Ԃ����Ƃ����������_�����ɏd�v�ł��B�F����̂Q�O�T�O�N�͂ǂ��ł��傤�B����Ȃɉ��������ł͂���܂���B���̎����␢�̒����̂��Ƃ��������߂Ă���̂ł͂Ȃ�2050�N�Ɏ��_��u���������͐^���ɘb�������K�v������Ǝv���܂��B���̊F����͂��낢��Ȑl�̘b���ĉ����������Ƃ��͂������Ă��܂��B�l���̒��łƂĂ���Ȏ������߂����Ă���Ƃ������Ƃ��l���ė~�����Ǝv���܂��B
�@�b�����Ƃ����͎��ł����A�����ȂƂ��납��Ă�Ęb���@������������Ă��܂��B���������ŊF����̑O�ɂ��܂����B�Q�Q�O�����̃X���C�h���g�������̘b�������̈�قňꐶ�����Ɍ��ĐÂ��ɕ����Ă��������Ė{���ɖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�������̍u������
1�N
��{���o�g�̐l���e���r�Ŋ��Ă���Ȃ�Ď�{�������k�Ƃ��đ�όւ�Ɏv���邱�Ƃł��B
���̍u������Đl�Ƃ̃R�~���j�P�[�V��������Ȃ��Ƃ�ŋ߂̓o�����t���[�Ȃǂ��N���Ɋւ��邱�Ƃ��厖���ƕ�����܂����B�l����{���w�Z�𐢊E�ɍL������悤�Ȑl�ɂȂ肽���ł��B
![]() �V���[�Y�@��y�Ɋw�ԁ@�A
�V���[�Y�@��y�Ɋw�ԁ@�A
����20�N4��25���@�ߌ�@��{���w�Z�̈��
�u�t�@���k�|�p�H�ȑ�w���p�������@�ԏ�O�Y����

�͂��߂�
���̐��܂�͉��ё��ŁA���̎�{���w�Z�ŎO�N�Ԋw�т��낢��Ȑ搶���狳���Ă����������Ƃ����Ă��������܂����B��{���w�Z���ƌ�A�D���ȊG��`���Ă��܂����B���̌ア�낢��Ȑl�̏Љ�ō������������ɂȂ��Ă�������Ύs�̕\�����u�ې���p�v�ɓ��Ђ����Ă����������Ƃ��ł��܂����B�����ŁA���̊Ԃɂ�����|�����̊G��`���Ă��܂����B
�F����͔��p�̎��Ԃɖ��G�␅�ʉ�ȂǑ����̍�i�����Ă����Ǝv���܂��B���́u�@�W�v�ɓ��{��̕���ŏo�i���Ă��܂��B
���{��́u��G�̋�v�ŕ`���܂�
���{��͂ǂ�ȑf�ނŕ`����Ă���Ǝv���܂����B�F����͂���܂Ő��ʉ���g���ĕ`����i�ɂ��Ă����Ǝv���܂����A���{��́u��G�̋�v�ŕ`���܂��B��G�̋�͎��R�łł��Ă��܂��B���̕ӂɎU����Ă������Ǝv���Ă����܂��܂���B�����ɁA�Ԃ��A���A�̐�����܂����L�k���g���܂��B�@�B�ōׂ����ӂ��Ō�͏��������ׂ����G�̋�̌��ɂȂ�܂��B�r���G�̋�͍���ɂȂ��Ă��܂��B�Z���߂̐F�قǍr�����q�ɂȂ�܂��B1�Ԃ���15�Ԃ��炢�̔Ԑ��������Ă���1�Ԃ������Ƃ��Z���F�ł��B����́u���s�X���Y���v�Ƃ����ł��B���{�ł͒������ł��B�ׂ����ӂ��Ă��Ƃ��ꂢ�ȌQ�F�ɂȂ�܂��B������́u�����h�E�R�E�v�Ƃ��������ꂢ�ȐF���Ƃ�܂��B�ΐF�́u�N�W���N�E�}���J�C�g�v���ӂ��ĊG�̋�ɂ��܂��B����Ɋ�G�̋�͉��M���邱�Ƃ���ĐF��ς��Ă������Ƃ��ł��܂��B�����F�́u�S�t���v���g���܂��B�ޗ��͉��y�Ȃǂł̊L�k�ł��B�L�k�����\�N������������Ɣ����ۂ��ϐF���Ă����܂��B������ӂ��Ă����Đ��ɂ��炵�A�������Ɣ��������ɂȂ�܂��B���Ђȗl�̊�ɓh�鎞�ɂ��g���܂��͉̂����Ƃ������̕��Ɛ|�����w���������ăI�V���C�ɂ��܂����B���{��ł͂قƂ�ǂ͊L�k�����Ď��Ԃ������ĊG�̋�ɂ��Ă����܂��B
���{��͘a���ɕ`���܂�
�R�E�]�Ƃ����̔���ςđ@�ۂ��ׂ������A�u�Ƃ�눨�v������Ď������w�ɂ����Ă���܂��B�����p�b�N�ł��������邱�Ƃ��ł��܂��B���Ȃǂ̑@�ۂ����Ɠ����悤�ȍ\���������Ă��܂��B���Ƒ@�ۂ͉����悤�ł����u�����v�Ƃ��u���v���̎悵�Ă��Ĕ���Ŏς�Ƃł��܂��B���Ď��J�ł�����������܂����B���䌧�E���E�R�`���ł��ł��㎿�Șa�������Y����A�O���[���Ƃ��l���[�g���̎�������܂��B���̖̔A�w�̔��G��`���x�[�X�ɂȂ�܂��B
��G�̋��a���ɐڒ�������̂��P�ł��B����͋�����Ƃ������̂ł��B�u�O��{�v�Ƃ����܂��B���̍ޗ��S��������O��{���Ƃꂽ���Ƃ��炱�̖��O���t���Ă��܂��B�P����������g���Ɗ���A���Ȃ�����Ɣ����ꗎ���܂��B���������o���������ς��ςނ��ƂŎ����̊G�̕`�������ł��Ă����܂��B
�ŏ�������{��Ƃ������킯�ł͂���܂���
6���I�̒����A�������璩�N������ʂ��ĕ������`����ė��܂����B�����`���Ƃ������e�Ŋw�K�����Ǝv���܂��B�����̓`���ƂƂ��Ɉ̂����V����A���t�Ƃ�����������������G��`�����肷��E�l������ꏏ�ɓ��{�ɓn���ė��܂����B�������L�߂邽�߂Ɏ����������܂�܂����B�����Ɏ��������Z�p���������܂�A�n�������ė��܂����B�����ɐΌA�Ɍ@��ꂽ����������܂��B���ܓ��{��Ŏg���Ă���G�̋�Ɠ������̂��ʐF�Ɏg���Ă��܂��B�C�������Ȃ��獡�ł��N�₩�ȐF���c���Ă��܂��B��N�O�ɂ͐F�͂�������܂���ł��������R����Ƃ����ޗ��ɐA���̐����������Ďg���Ă��܂����B
��������ɐ�M�Ƃ������n��Ƃ����āA���̑D�ɏ���Ē����ɕ��ɂ����܂����B��M�̋A����A��������̊G�t���A���┓���ӂ�Ɏg����࣍��ȏ�lj��`���܂����B�]�ˎ���͍����������܂������A���{�����͊G��̕����E�Z�p���p������G�敶�������W���܂����B�k�ցE�̖��ȂǁA�����̎������������G�t���������{�̔��p���x���Ă��܂����B��������ɂ͖��G�������ė��Ă����A����܂ł̓��{�̊G�����{��ƌ����悤�ɂȂ�܂����B
�����̍�i�ɂ��Ęb���܂�
�����i��͍��Z��ł���R�`�~�n�œ���Ԃ��炢�����ĕ`�������̂ł��B�R�����S�ł����A�[���������p�ƒ��ޕ��p�������������ĕ`���Ȃ������̂ł��B�G��`����ň�ԑ厖�Ȃ��̂��X�P�b�`�ł��B�X�P�b�`����Ԋy���݂ł����A�h���͕̂`���o���ł��B�ǂ�����`������悢���Y�ނƂ���ł��B��������Ă��Ă��`���Ȃ��Ƃ�������܂��B��ԍD���ȂƂ��납��`���n�߂܂��B
��������`���Ƃ��͑�ςł��B��������ł��B�����`�����Ă����Ƃ�������܂����A��C�܂�܂鑨����͎̂���̋Ƃł��B�Ȃ������G���ł��Ă��܂���B���̂��ߕ����������ς��X�P�b�`���܂��B�����̒��ŗl�X�ȁu�����v���J��Ԃ��Ă����̂ŏ�����܂��B�厖�Ȃ��Ƃ͎����̑Ώە������`�[�t�������߂�u�C�����Ɗ�v���ƂĂ��厖�ł��B������́u����������Ɛh�����Ă݂悤�B�v�Ƃ����C�����ł��B���܂��`���K�v�͑S�R����܂���B
������͉H���R�̊G�ł��B����̌d�����ƂĂ����ꂢ�ł��B�Ђ킾�����w�̂����������w���d�˂������ŁA���������Ƃ����X�̒��ł́u�ځ[���v�Ɣ��������܂����B�����Ȃ肨�����낢�ȂƎv���ĕ`���Ȃ��Łu���Ŕ����̂��낤�v�Ǝ����ɖ₢�����Ă݂�B�����܂܂������`���̂łȂ��S�̒��Łu���ł����̂��낤�v�Ɩ₤���ƁB���͂��̂��Ƃ�厖�ɂ��Ă��܂��B�������Ȃ��ƍ�i���ł��ďオ���Ă����Ƃ��ɑ厖�Ȃ��̂��Ȃ��Ȃ��Č`���ʂ��Ă��܂������ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�G��`���Ƃ���ԑ厖�Ȃ��Ƃ͋Z�p�ł͂���܂���B�Z�p�͓�ԖځE�O�Ԗڂł��B�����������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł�����u���`�[�t�ƌ����������Ɓv�u�X�P�b�`�����Ă��炤�Ώە��Ƙb������悤�ȋC�����v���厖�ł��B
�������̉،��̑�ɏ\����G��`���ɍs�����Ƃ��́A���܂�Ɋ����ĊG�̋��n�������������Ă��܂��قǂł����B����Ȓ��Łu�������ǂ���������Ɗ撣���Ă݂悤�v�Ǝv���đ����܂����B�����Ɍ���ŊG��`�����Ƃ̈Ӗ�������܂��B
�������̃`�x�b�g������ɉ��x���X�P�b�`�ɂ����܂����B���������������ꂢ�ł����B��`�ɍ~�肽�Ƃ����̋߂��������܂����B�G��`���̂Ɍ��t�͕K�v����܂���B���n�ňꐶ��������Ă���Ɛl���W�܂��Ă��܂��B��������Ȃ��`�x�b�g�����ŃG�x���X�g���X�P�b�`���Ă��������m��Ȃ������ɐl���W�܂��ė��܂����B���炫��ƋP���Ί炩��g�������̂�������ė��܂����B�u�����v�������܂����B
���O�ʐ�10������@�����k�サ�܂��B�����܂��Ă���l������`���܂����B�����������̓������Ȃ߂炩�ł����B������������ł��B
�@���l�p�[���ŕ`�����G�ł��B��s�J�g�}���Y�͗��j�����蒤������������܂��B���̊G�͏��������ʒu���猩�Ă��܂��B�����^�����ʂ��猩��K�v�͂���܂���B���Ղ�����A���グ���肵�܂��B�l�̎G�����`�������č\�}���l�����̂��̂ł��B�[���ł͂Ȃ������ł̂����[�����ۂ�������A�G�̐^��n�ʂɂ����肵�܂����B
���R�`�̏�R�ɏZ��ł������A�{�Y�_�Ƃ̕��ƗF�B�ɂȂ�A�q�������܂ꂽ���猩�ɂ��o�łƂ����Ă����ŕ`�������̂ł��B�u�ْ����v�@�u�ё��̏_�炩���v�@�u���킢���v��`�����������G�ł��B���̖ڂ̐��ɂ҂���Ƃ������̂�`�����ƈӐ}���ĐԂ����Ă݂���i�ł��B
�@�����̍D���Ȃ��̂ɂ�������O�����ɂ������B���͒��X���Ȃ����̂ł͂Ȃ��̂ł����ꐶ�����ɂ���Ă��邱�Ƃ͂ƂĂ������������Ǝv���܂��B
�G��`�����@�ɐ�͂���܂���
�O�i�K���X�P�b�`�ł��B�G���ǂ��܂Ƃ߂邩�������l���Ă��܂��B�����Ԃ̒��ɒu���Ă��܂����������u�͂�����̃X�P�b�`�u�b�N�v�����ɓ���Ă����܂��B���n�ōl�����܂Ƃ߂�Ƃ�������܂����A��w�̎��Ƃ̍��ԁA���т�H�ׂĂ���Ƃ��A�X�P�b�`�̈�ۂ����\�����`������ł����܂��B���ꂾ���ŕ`����Ƃ������Ƃł͂���܂��A��������邱�Ƃň��S�������܂�܂��B���������́A�������̂悤�Ȃ��̂������ς��`���Ă�������������Ă݂���A�����������Ă݂��肵�܂��B�������̂��ł���Ɖ�ɓ\���ďc���̐��������ĉ����̈ꂩ�ɂ���܂��B�r���G�̋�Œn�h������A�ؒY�Ȃǂʼn����������A�n�������ĂȂ���܂��B���̌�ʐF�����܂��B����ɂ�������̉�ނ������čs���ĕ`�����Ƃ͂ł��܂���̂ŁA���ʉ�A�ʐ^�ȂǑf�ނ������ς������Ă��āA�Ƃł�����������Ďd�グ�܂��B�W����ł͈���Č����܂��B
�G��`�����@�ɐ�͂���܂���B�C�����A�����A�l�����A�����̌�����ۂ�`���o�����Ƃł��̐l�̊G�ɂȂ����Ă��܂��B
���ɂȂ��邽�߂�
�F����͍�12�E�R�ł��B�Ƃ��Ă��������̂������Ă���Ǝv���܂��B����ɂȂ��邽�߂ɂ͈ꐶ�����ɂ����Ȑl�Ƙb���A�u���ꂵ���ȁv�Ƃ��u�����ȁv�Ƃ����̎��̂Ȃɂ��Ȃ��C�������ɂ��Ă������Ƃł��B
�����͂���Ȏ����ł����̂��Ǝv���Ȃ���F����ɘb���܂����B
�����̎����Ă��邢�����̂ɓ������邱�Ƃ���ł��B�݂�ȕ������Ă��܂���������������T���Ă��������B
�{�N�x��{�̋���̏d�_�u���Ȕ����E���ȊJ���v�̗͂����߂�M�d�Ȋw�K�̏�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂����B
���k���z���@�@�@�P�@�N
���낢��ȕ�������݂邱�Ƃň�����G�Ɍ����邱�ƁA��������`���ė��K���Ă���`���Ƃ������ƁA�����܂܂̊G��`�������łȂ��Ď����ōH�v���ĕ`���Ă��邱�Ƃ���ۂɎc��܂����B�����̍D���Ȃ��Ƃ��珫���̐E�Ƃɂ��Ƃ��A�͂��߂��琬������킯�ł͂Ȃ��āA���s���āA���̂��Ƃ����Ď��ɒ��킷�邱�Ƃ�����Ǝv���܂����B
�V���[�Y�@��y�Ɋw�ԁ@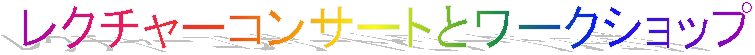 �B
�B
�`�@�̂��y�����ƃI�y���̖����@�`
�I�y���̎�@�O�Y�����@����i�o�X�E�o���g���j
�s�A�j�X�g�@�����T�q�@����i�s�A�m�j
�����Q�O�N�P�O���Q�Q��
���Ύs����{���w�Z�@�̈��
�S�Z���k�Ώۂ̍����w�������J���b�X����
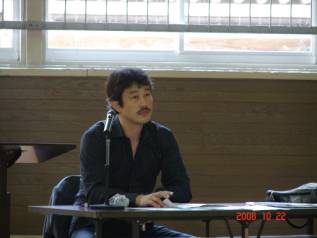
�P�O���R�O���`�P�Q���P�O��
�O�Y��������E�����T�q����̃~�j�R���T�[�g

�P�R���S�T���`�P�S���R�O��
�N
�N
��{���w�Z�Z�́@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�@�q��
�N
�N
�r��̌��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�����Y
�N
�N
���Ƃ����є��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���F
�N
�N
��̕��ɂȂ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�V��@�@��
�N
�N
�A��\�����g�ց@�@�@�@�@�@�@�@�@�f�E�N���e�B�X
�N
�N
������Ȃ������̒��X
�I�y���u�t�B�K���̌����v����@�@���[�c�@���g
�N
�N
�����m�̉�
�I�y���u�J�������v����@�@�@ �r �[ �[
���k�̊��z�����
��N��
�@���͎O�Y����̍����w���������ċz�ʼn̂��̂��Ɛ����傫���Ȃ邱�Ƃ�m��܂����B���i�͓��ɋC�ɂ��Ă��܂���ł������A�ӎ����Ă݂�ƕ����ċz�����Ă��Ȃ����ƂɋC�Â��܂����B���̗��K����́A�̂��Ƃ��ɕ����ċz�����ĕ����琺���o�����Ƃ��ӎ����܂����B�������ň�N���͗D�G�܂��Ƃ邱�Ƃ��ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�ߌ�̎O�Y����ƍ�������̃R���T�[�g�����炵���̐��ƃs�A�m�ŁA�ƂĂ��������܂����B���ɂƂ��āA����̍����w���ƃ~�j�R���T�[�g�͒��w�Z�����̑�Ȏv���o�̈�ƂȂ�܂����B
���̒��ڂ̐�y�œ��{�͂������̂��Ɛ��E���Ŋ���Ă���������邱�Ƃ�m��A�������O�Y����̂悤�ɂȂ肽���Ǝv���܂����B����̑̌�����������̊w�Z�����ɖ𗧂ĂĂ��������Ƒ����܂��B
��N��
�@�@�O�Y�l�̒��J�Ȏw���̂������ŁA�������̃N���X�͂��̌�傫���i�����A�{�Ԃɂ͒j�q�̐����ǂ������A���ʂ͗D�Ǐ܂ł������[���̂������������グ�邱�Ƃ��ł��܂����B
�R���T�[�g�ł́A����l�̑��̍������̂Ɣ��t�Ɋ������܂����B���Ɛg�U���U��ŕ\����L���ɂ��Ă���O�Y�l�A�s�A�m�ł��̕\��������ɍۂ������Ă��鍂���l�A�ǂ�����f�炵���A�����Ă��ĂƂĂ��킭�킭���܂����B
���͍��̃R���T�[�g���āA�����Č��āA��������l�̂悤�Ɏ���̐l�������Ί�ɂ��邱�Ƃ��ł���l�ɂȂ肽���Ǝv���܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�O�N��
�@�v���̕��ɍ��������w�����Ē����̂́A�������ɂƂ��āA���߂Ă̑̌��ł����B�������A�O�Y����̂��w���͂ƂĂ��������₷���A�����ɐ����������ł��܂����B�O�Y����̂��w���̂������Ō���s��ꂽ�����R���N�[���ł́A�S�ẴN���X���̈�قʼn̐����������邱�Ƃ��ł��܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���w���̌�̃~�j�R���T�[�g�ł����������̐��ƃs�A�m�́A�������̐S�̒��ɂ��܂ł��c���Ă��܂��B
���͊��ɒm���Ă����Ȃł��A�v���̕��X�̃R���T�[�g�ł͑S���قȂ�����ۂ��鎖�ɋ����܂����B�܂��A�ȂɊւ��邨�b�������[�����̂���ł����B �u�K�v�̂Ȃ����Ȃ͂Ȃ��v�Ƃ��������b�͂��ꂩ��̐������ŎQ�l�ɂȂ�܂����B�D���������ɗ͗}���āA��������ɂ��čl���Ă䂫�����ł��B
�O�Y��������ɂ���
��{���w�Z�̏��a�S�V�N�x���i��P�W�Ɛ��j
���݁A�I�y���̎�Ƃ��đ����Ŋ��Ă���B �i�����̌��c���A���{���t�A������A���b�V�[�j���ۃI�y���R���\���\���ܓ��j �w�Z�ւ̌|�p�Ɣh������ �A��t�s���Β����w�Z
�A��t�s����J���w�Z �A��z�s����k���w�Z
�@�@���ڍׂ̓z�[���y�[�Whttp://miura.music-web.info/���������������B
�����T�q����ɂ���
�@�C�^���A�I�y���A�s�A�m����ɂ��A�w�Z�ւ̌|�p�Ɣh������
�ł͎O�Y��������̔��t�߂Ă���B
�@
�Q�l�����@�����Q�O�N�x�u�w�Z�ւ̌|�p�Ɣh�����Ɓv�i���������Ɓj
�y��|�z�i�w�Z�ւ̌|�p�Ɣh�����Ƃ̉���v�̂��j
�@���̎��Ƃ́A�����E���k�������|�p�����̊y�����₷�炵����m��@����[������ƂƂ��ɁA�w�Z�ɂ����镶���|�p�����̊�������}�邽�߁A�D�ꂽ�������s���Ă���|�p�Ƃ�`���|�\�̕ێ��҂Ȃǂ��w�Z�ւ̕�����g�Ƃ��Ċw�Z�ɔh�����A�u�b����Z��I�Ȃǂ��s�����Ƃɂ���āA�L���ȐS�Ɗ�������ނ��Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B
�y���e�z
�@���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z���ɁA���̊w�Z���ݒu����Ă���n��o�g�̌|�p�Ƃ�`���Z�\�̕ێ��҂Ȃǂ�h�����A�̈�ٓ��̊w�Z�{�݂����Ƃ��āA�����E���k�⋳���A�ی�҂�ΏۂɁA�����|�p�Ɋւ���̌��k��n��̌ւ�Ȃǂ̍u�b�ƊȒP�Ȏ��Z��I�����s���܂��B
�V���[�Y�@��y�Ɋw�ԁ@�C
����21�N�X���P8���i���j�P�R�F�R�O�`�P�T�F�P�O
�u�t�@�����f�U�C�����[�N�X�@�X�R�@�ꗝ�@����
�`�@�S�ɕ`�������͕K����������@�`
�@�{�Z���Ɛ��Ō���Q�C�R�N�����E��̌��ł����b�ɂȂ�X�R���炲�u�������������܂����B���邢���l���Ɛe���݂₷�����b�Ő��k�����́A���������Ƃ̑���⓭���Ď����邱�Ƃ̑�ς���������邱�Ƃ��ł��܂����B

�R�N�@���q
�@�����A�����Ɂu���v�u�ڕW�v�������Ƃɂ���āA���邢��������J����邩������Ȃ��B
�@�ڕW��B�����邽�߂ɂ́A���X�w�͂��邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ�������܂����B�����A��ɁA�����̎�ɖv��������A���Z�������ȏ�ʂŐ��������Ƃ̂ł���E�ƂɏA������ƂĂ��y�����l�����҂��Ă���Ǝv���܂����B�d���ɏA�������́A�ǂ�Ȏd���ł��ꐶ�����Ɏ��g��ŁA���������Ă����l�ɍD��ۂ������Ă��炦��悤�ɂȂ肽���Ǝv���܂����B
�R�N�@�j�q
�@�}�i�[�u���ł́A���ۂɁu�������v�̗��K������̂��Ǝv���܂������A���ۂ��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������̂ŁA���܂茘���Ȃ炸�ɘb�����Ƃ��o�����B�X�R���Ō�̕��ɘb���ꂽ���Ƃ́A���ꂩ��̏����ɑ���Ǝv���B�ŋ߁A�����A�w�`�̒����K�̂��߂ɑ����w�Z�ɂ����̂ŁA�����Ȑ搶�ɐϋɓI�Ɉ��A���������Ǝv���B���ꂩ��A�����̎�A���Z���������A�����ւ̖ڕW�������A���ꂪ�����ł���悤�ɁA�}�i�[�Ȃǂ��ɂ��Ȃ���A�撣���Ă������Ǝv���B
�V���[�Y�@��y�Ɋw�ԁ@�D
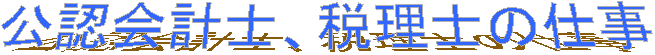 |
����21�N�P�P���@�T���i�j�@�W�F�R�T�`�P�T�F�P�O
�u�t�@�@�u���C���@�X�^�b�t�@�ؒJ�@�q�Y�@����
�`�@�l���̃o�b�^�[�{�b�N�X�Ō������O�U�͂���ȁ@�`
�V���[�Y��T��ڂ͌o�c�R���T���^���g�̒ؒJ�q�Y����w�N�ʓ��ʎ��Ƃ���ёS�Z�u�������������܂����B���ʎ��Ƃ͎����o���ōs���܂����B����ڂ͈�N���Ɂu��Z�̎v���Łv�A�O���ڂ͓�N���Ɂu���S������͂�����ׂ��������v�A�S���ڂ͎O�N���Ɂu���Z�����ĂȂ낤�v�����ꂼ��e�[�}�Ɏ���e�L�X�g���g���Ď��Ƃ�����Ă��������܂����B�u���ł́u�Љ�ł͒N������Ɨ������`�ŃW���b�W����d�����K�v�v�u�N�[���w�b�h�A�E�I�[���n�[�g�A��Âȓ��ŔM���S�������Ă��q�l�ɐڂ��邱�Ƃ���v�ƌ�肩���Ă��������܂����B
�@
���k���z���
�R�N
���ȏЉ�������������납�����ł��B�ŗ��m�̕����ƕ����Ă����̂ł����Ɠ���͂Ȃ����ȂƎv���Ă����̂ɁA�ؒJ��������邭�������낢���������̂Ŋy�����߂������Ƃ��ł��܂����B�S���̎��Ƃ��y���������̂ŁA���҂��Ă��܂����B�S���Ƃ͂܂��Ⴄ�b�������ėǂ������ł��B�u��ł�����v�̘b�Ƃ��A�����Ă��Ċm���ɂ������ȂƎv���܂����B��Ԉ�ۂɎc���Ă���̂́A���ӕ���̐l���̃o�b�^�[�{�b�N�X�Ō������O�U�͂���ȂƂ������t�ł��B������ŏ��Ɍ����Ƃ��A���Ԃ��ɂ͖������ȂƎv���܂��܂����B�ł��A���̌�̓��ӕ���
�łƂ������t��ؒJ����̘b�Ŋ撣���Č��悤�Ǝv���܂����B������܂��A�����̓��ӕ���������邱�Ƃ���n�߂悤�Ǝv���܂��B�����������͌������Ȃ��悤�Ɋ撣��܂��B
�R�N
���Z���́A�����̕����悭�Ƃō���Ă���̂����Ă����̂ŁA��������Ƃ����C���[�W���ƂĂ����������̂ł����A�ȒP�ŕ�����₷���}���g���������̂��A�œ����g�����ƂȂ������ł����̂ŕ����₷�������B���͍����A���F��v�m�Ƃ����d�������߂Ēm��܂����B����̋C�����𗝉����Ȃ���������̐��`����ʂ��A�N�[���w�b�h�E�E�H�[���n�[�g�ő���̐l��[��������Ƃ����d���́A�Љ�ł��ƂĂ���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B�����̍u�����Ď��̓N�[���w�b�h�E�E�H�[���n�[�g�Ƃ������t����Ԉ�ۂɎc��܂����B���ʃN�[���w�b�h�̐l�Ȃ��ł�������ӁA�l�Ƃ̕t���������������C���[�W���������l�������ł����A����Ȑl��������v�����Ȃ���K�ȃ��b�Z�[�W��`����E�H�[���n�[�g�����ĂΒN������M������鋭�͂Ȑl�ɂȂ��Ƃ����͎̂��������撣��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C���������Ă��܂����B